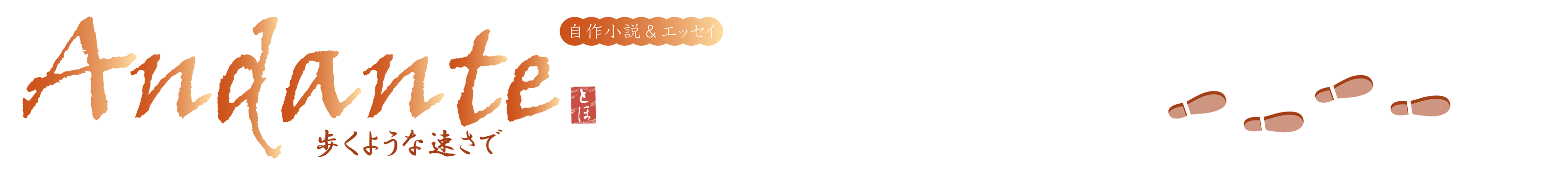第1回 夕暮れのガーダー橋
ある夏の日、僕らは車を走らせて故郷の町に向かっていた。助手席と後部座席にいるのは幼なじみの悠太と篤志だ。高速を使えば暗くなる前にあの場所に到着できるはずだ。
「俺たちの思い出の場所に行ってみないか?」
言いだしたのは悠太だった。
子供の頃、北海道の日高地方にある厚賀という町に住んでいた。日高地方の海沿いには、苫小牧から様似まで鉄道が伸びていた。全長140キロメートルに及ぶ、JR北海道の日高本線だ。とは言っても単線で一日に数回、一両か二両の気動車がゆっくり往復するだけのローカル線であった。しかし、広大な海沿いの原野に一本だけ伸びる線路をトコトコと走り抜ける姿は非電化路線ならではの光景だった。優駿浪漫の異名をとる青い車体のディーゼル列車は、大自然のなかで人間がいかに小さな存在なのかを僕らに教えてくれたのだと思う。
自称、鉄道オタクの篤志は今も列車を追いかけているらしいけれど、彼が、「日高本線の雰囲気はどこの列車もかなわない」と断言するのもわかる気がする。僕も、何も考えずに列車に揺られていたいとき、迷わずに日高本線を選ぶことだろう。
夏になると日高の海沿いでは一斉に昆布漁が始まる。昆布干しのすぐ脇を列車が走っていても、地元の漁師たちは一向に気にするようすもなく作業を続けていたものだ。
新冠まで行くと競走馬のサラブレッドを放牧する牧場が増えてくるのだけれど、その馬たちもまた、柵のすぐ脇を列車が走っていても、まったく気にする様子もなく草を食んでいる光景を目にした。それだけ日常に溶け込んで存在している路線だったのだ。夏の日高はその地名の通り、日が高く、青空が澄みきっている。そんな空の下を走る優駿浪漫が僕らは大好きだった。
日高本線の駅はほとんどが無人駅で簡素なつくりのものが多く、民家に溶け込んで建っているものが多かったから、地元以外の人が国道沿いを車で走っていても見つけるのはなかなか難しかったと思う。その点、僕らの家の近くにあった厚賀駅は木造ながらとてもセンスのいい建物で駅の看板は手で彫った彫刻でできており、玄関の上のアーチ型の屋根も特徴的だったから地元の僕らにとってはちょっとした自慢だった。
そんな日高本線だったけれど、海沿いぎりぎりに作られた路線であったため、海水の浸食により次第に存続が危ぶまれる状態になった。度重なる台風や土砂災害の影響で一部の線路が損壊し、長らく休止状態だったけれど、赤字路線だったこともあり復旧工事の見通しは立たなかった。そして今年、ついに正式に廃線が決まってしまったのだった。それで、この機会に三人で故郷を訪れてみることにしたのだった。

厚賀駅と大狩部駅の間には大きな川が流れていて、そこでよく三人で泳いだり、釣りをしたりして遊んだものだった。その川の河口には、鉄道のガーダー橋が架かっていた。ガーダー橋とはいわゆる桁橋のことであり、横にかけた橋桁によって橋面を支える方式で作られた橋のことである。海に流れ込む川が多い日高本線にはいたるところにこのガーダー橋が架けられていたのだった。
僕らは川での遊びに疲れるとよく線路の上にのぼってこのガーダー橋を渡り、その橋のまん中で海に沈む夕日を眺めて語り合った。海からやってきた無数のカモメたちがいつも僕らを楽しませてくれた。列車がやってきたら逃げ場所もないから、一斉に川に飛び降りるしかない。ずぶ濡れになりながら、僕らは川の中で大声で笑いあったものだ。近くには踏切もなかったから波の音がうるさい時は列車の音に気づかずに、大きな汽笛の音を鳴らされることもあった。
橋が見渡せる丘に到着すると、僕らはゆっくりと車を降りた。夕暮れ時の空のグラデーションが川面に反射して、ガーダー橋のシルエットが浮かび上がる。この思い出の橋に、もう列車が走ることはない。
聞こえるはずのないディーゼル音を感じながら、僕らはいつまでもその場所に佇んでいた。
(了)

 北野とほ (Kitano Toho)
北野とほ (Kitano Toho)
自作小説&エッセイを勝手に不定期連載してます。
雪国在住です。野山を歩くのが好きです。





Copyright(c) 2023 アンダンテ All right reserved.