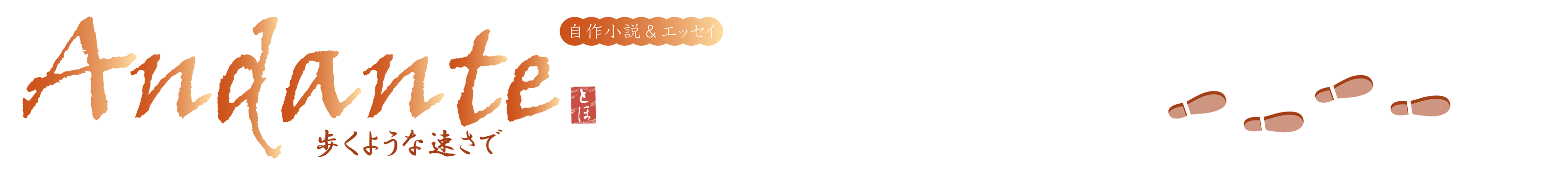第5回 みかん
悠作が家庭教師をしている家のお母さんがノートパソコンを買った。話題のWindows95を搭載した最新モデルだ。インターネットというものもできるようだ。セット販売でデジカメも一緒に買ったと話していたけど、なんと120万画素の高画質らしい。いわゆるメガピクセルというやつだ。
実は悠作もこないだ、大学の友人から古いパソコンを譲り受けたばかりだ。せっかくパソコンを入手したのだからと、別の友人からWindows95のセットアップ用のフロッピーディスクを借りた。何十枚もあったから、途中で「ディスク23を挿入してください」などというメッセージが出る。順番を間違えないように奮闘しながらなんとかインストールすることに成功した。しかし何しろハードディスクの容量が400MBしかなかったから、余分なデータはすべて削除しなければならなかった。ワープロに使うフォントも明朝とゴシックの二つだけに減らしてしまった。
デジカメも欲しかったのだけど、お金がなくて買えるはずもないので今まで使っていたバカチョンカメラで我慢することにした。それでもとりあえず、インターネットだけはやってみようと家電量販店でモデムというものを買ってきたけど、モデムを買っただけではだめなことが判明した。プロバイダーというインターネットサービスに契約しなければならないのだ。悠作はさっそく友人に聞いて、市内にあるおすすめのプロバイダーに電話した。あと数日してプロバイダーからパスワードなどが書かれた葉書が届けば、ついにインターネット開通だ。悠作の9畳一間の狭いアパートの一室が、パソコンという長崎の出島によって世界とつながるのだ、なんて素晴らしいのだろう。あっそうだ、近くのNTTの窓口に出かけてテレホーダイの契約もしないといけない。テレホーダイに加入すると、あらかじめ指定しておいた市内の電話番号への夜間の通話料金が定額となるのだ。たしか夜の11時から朝の8時までが定額の時間帯だ。インターネットに接続するのにも電話料金がかかるからこういうサービスを利用しない手はない。

一方、家庭教師先のお母さんは、初期設定からプロバイダー契約、電子メールの登録まですべて業者にやってもらっていた。しかしすべて他人任せなので最初から使いこなせるはずもなく、まるでチンプンカンプンといった様子であった。
家庭教師先の教え子は浩紀(ひろき)といい、一人っ子の小学校六年生だった。学業成績はまあまあだったけど、性格のいい素直な男の子という感じだ。小学生のうちから悠作のような家庭教師を雇うというのだから、この家庭の意識の高さがうかがえる。お母さんは専業主婦だけれど、PTAの役員をしているそうだ。小柄で見るからに上品な感じがする、いかにもお嬢様育ちという印象だ。東京の女子大を卒業したと言っていたのもうなずける。お父さんはどこかの大きな会社の役員をしているそうだけど、仕事が忙しくて滅多に家に帰って来られないらしい。職場に寝泊まりでもしているのだろうか。実際、悠作もお父さんの姿を見たことはほとんどなかった。
悠作は毎週日曜日に家庭教師先の家を訪れ、浩紀に数学と英語を教えていた。貧乏学生だった悠作は車は持っていなかったけど、その代わり学生ローンで買った250ccのバイクに乗っていた。250ccのバイクは車検もいらないし、高速道路に乗ることもできる。一番コスパのいい排気量だ、と悠作は思っていた。浩紀はそのバイクが気に入っているらしく、いつも後ろに乗せてくれとせがんできた。そのために悠作は小さめのヘルメットを中古ショップで購入したほどだ。
家庭教師の勉強の前には、いつも夕食をごちそうになっていたのだけど、それもお母さんのはからいだった。貧乏な大学生にとって、この日曜日の夕食がとても貴重だったのは言うまでもない。
ある日の夕食はカレーライスだった。その日はなぜか、お母さんがやたらと味について感想を求めてきた。
「今日のカレー、いつもと違いません?」
正直いうと、悠作はあまり味の違いを感じなかったのだけど、肉の代わりに別のものが入っていた。なんだろうなと思っていたら、
「それ、フグの唐揚げなんです」
お母さんが嬉しそうに言うのだった。悠作はびっくりしてカレーを吹き出しそうになった。さすが、お金持ちの家は違う。カレーの辛さのせいで味はまったくわからなかったけど、それが悠作の人生における初フグであることは間違いなかった。
「どうせなら、テッサとかテッチリで食べたかったなぁ」
悠作は少しだけ思ったけれど、もちろん口には出さず心の中にしまっておいた。そしてあの時の嬉しそうなお母さんの笑顔を思い浮かべていた。
秋になって、大分寒さも増してきたときのことだった。悠作は家庭教師先での勉強を終えて帰ろうとしていた。玄関先に止めたバイクにまたがってエンジンをかけ、ヘルメットをかぶろうとしていたとき、突然お母さんが玄関の外に出てきて、悠作の腕をつかんだ。
「先生、今日はもう少しだけ家にいてくれませんか? パソコンを教えてほしいんです」
お母さんは新しいパソコンを買ってしばらく経つのに、デジカメで撮った写真の保存の仕方もよくわからないと言っていた。それが何かの口実であったことを、その時の悠作は気がつかなかった。どうせ家に帰っても大してやることもないし、いつも夕食をごちそうになっているからと、悠作は快くその申し出を受け入れたのだった。
お母さんはデジカメの電源を入れると、たまたまテーブルにあった、みかんの写真を撮って悠作に見せた。適当に撮ったにしても被写体があまりに左側にずれていてへんてこな写真になってしまった。それをみてお母さんと悠作はお互いの目をみて笑いあった。そのとき悠作はお母さんの笑顔が素敵だな、と温かい気持ちになったのだった。
年が明けた頃、悠作はお母さんから、一泊二日で家族旅行をするから一緒にどうかと誘われた。いつもは仕事で忙しいお父さんもやっと休みが取れたとのことだった。
「せっかく親子三人の家族水入らずの旅行なのに僕が行ってもいいのかな」
悠作は思ったが、お母さんがどうしてもとしつこく頼んでくるので、それならば是非と言葉に甘え、最終的に了承したのだった。
家族旅行の行先はスキーで有名な町だった。その中で一番大きなスキー場の近くに別荘があるとのことだった。あの辺りのエリアは最近海外の資本がどんどん入っていて外国人観光客も多く、地価も急上昇していると聞く。その別荘も相当値上がりしているのは間違いないだろう。悠作はまた余計なことを考えた。
家族旅行の当日、悠作はスキーを担いで地下鉄とバスを乗り継ぎ、家庭教師先の家に行った。家の前では浩紀が待っていた。旅行の前だというのにどこか、少しつまらなそうにも見えた。
「お父さん、来ないって」
悠作の顔を見るなり、浩紀は言った。せっかく家族でのスキー旅行で休みも取れたと言っていたのに、急な仕事でも入ってしまったのだろうか。
「あの人、いつもそうなんです」
そこに現れたお母さんが眉をひそめて言った。
「もともと来ないんじゃないかと思ってたんです。仕事が優先で。しかもそれ以外にも理由があるみたいで…」
なんか意味深な発言だった。旅行は中止になってしまうのかと思ったら、浩紀が楽しみにしているからと、予定通り行くことになった。
別荘は立派な二階建ての、木造の建物だった。一階の広い居間の奥に対面キッチンがあって、それがバーのカウンターとしても利用できるようになっていた。広い窓からはスキー場の様子がよく見える。夜になるとナイターの明かりできれいな夜景が見えるのだろう。
別荘につくと浩紀はすぐにスキーに行きたがった。本当は悠作はちょっと一息ついて別荘の様子をもっと見たかったのだけれど、やっぱり今日の旅行の主役は浩紀だ。お母さんに車でスキー場まで送ってもらってリフト券を購入すると、二人でゴンドラに乗り込んだ。
「お父さん、来れなくて残念だったね」
悠作が声をかけた。
「いいよ、別に」
浩紀はゴンドラの外を見ながらつぶやいた。
「先生みたいな人がお父さんだったらよかったのに。お母さんだって時々そう言ってるよ!」
初めて聞いた事実に悠作は驚いた。あのみかんの写真を撮ったときの、屈託のないお母さんの笑顔が脳裏に浮かんだ。
それから悠作と浩紀は途中で休憩をはさみながら何本かスキーを滑った。さすが小学校六年生ともなるとスキーの技術もかなりのものだ。もしかしたら悠作よりも上手いかもしれない。
周りも暗くなってきてナイター営業が始まろうとするころだった。ちょっと目を離したすきに浩紀がどんどん先に滑っていった。スピードが出すぎて制御できなくなった浩紀はコースを示すポールにぶつかって転倒してしまった。
「大丈夫か!!」
悠作は必死に浩紀のあとを追った。
スキーが外れて数十メートル下で浩紀は止まった。悠作はスキーを拾って浩紀のもとに滑り寄った。幸い意識はあるようだったけれど目は閉じたままだった。
「おとうさん…」
浩紀がそう言ったように聞こえた。本当はお父さんに来てほしかったんだよな、と悠作は思った。念のため浩紀を医務室に連れていって診察を受けたけれど幸い異常はないとのことだった。医師の説明を聞いて悠作は心の底からほっとしたのだった。それから医務室の公衆電話から別荘にいるお母さんに電話で連絡し、車で迎えに来てもらった。
夕食は近くのレストランで食べる予定だったのだけどキャンセルして、別荘の居間で買ってきたコンビニの弁当を食べた。お母さんは「すみません」と謝ってくれたけれど、悠作も疲れていたからその方が却ってよかったのかもしれない。
食事を食べたあと、浩紀は奥の部屋ですぐに寝てしまった。無理もない、さんざんスキーを滑ったあとであんなことがあったのだから。
「ビール飲みません?」
夕食を終えた悠作に向かって、明るい笑顔でお母さんが言った。対面キッチンの後ろの冷蔵庫にたくさんの缶ビールが冷えているらしい。
お母さんは冷蔵庫からビールを出して悠作に手渡した。しかしそれは長い間冷蔵庫に保管されたままのビールだったらしく、缶の底を見ると、一年ほど賞味期限が過ぎてしまっていた。悠作は愉快な気持ちになって大声で笑った。その姿をみて、最初は申し訳なさそうにしていたお母さんも、その上品な顔でくすくすと笑っていた。
「わたし、お風呂に入ってきますから、賞味期限切れですけど、ビール飲んで待ってて下さいね」
それから一人、カウンターで賞味期限切れのビールを飲んでいた悠作はいろいろなことを考えていた。なぜ、お父さんは来なかったのだろう。もしかして、最初から来る予定ではなかったのではないか。お母さんはそれを知っていてわざと僕を誘ったのではないだろうか…。悠作は余計な詮索はしないでおこうと首を横に振った。
それからしばらくして日中の疲れがあったせいか、悠作は缶ビールを片手にカウンターでうとうとし始めていた。ふと気づくと、隣にお風呂上がりのお母さんが座っていた。ネグリジェ姿で、細い腕と脚が、薄い生地の端から出ている。悠作はこれまで飲んでいたビールの酔いがすっかり醒めていくのがわかった。心臓の鼓動が止まらなかった。ドキドキしている悠作の横にお母さんはその身体を寄せてきた。柔らかな胸の感触が悠作の腕に伝わる。お風呂上がりの石鹸のいい匂いがした。
「主人、職場の近くにマンションを買ったんです。家の近くだから帰ってこようと思えばすぐ帰って来れるはずなんですけど」
お母さんはおもむろに話し始めた。
「誰か、若い女の人と一緒に住んでいるのかもしれません」
悠作はかける言葉も見当たらず、ただ黙っているしかなかった。その姿をみてお母さんは急に話題を変え、明るい表情でこう言った。
「わたし、やっと電子メールが使えるようになりましたの。よろしければ先生のアドレスも教えて頂けません?」
悠作は混乱していたけれど深呼吸をして心を落ち着かせた。たしかに悠作も、せっかく苦労してインターネットを始めたのに、友人との連絡はポケベルがメインで、電子メールは全く使ってなかったのも事実だ。細かい連絡事項などは電子メールでやりとりした方が便利かもしれないと思って、悠作はアドレスをお母さんに伝えたのだった。
その夜、悠作は心地よい眠りについた。スキーの疲れもあったかもしれない。お母さんのほのかな香りが悠作の首筋に漂っていた。
旅行から帰ってしばらくの間、お母さんとのメールのやりとりが続いた。だいたいは日常のとりとめのない内容がほとんどで、特別なことはなにもなかった。
それから春が来て中学校に進学するとき、浩紀は有名学習塾に通うことになった。その機会に、悠作の家庭教師としての役目は終わった。もう家庭教師先に行くこともなければ、お母さんに会うこともないのだ。

新学期が始まってしばらくたった日のことだった。悠作はいつものように時刻が午後11時になるのを待ってパソコンの電源を入れた。ダイヤルアップネットワークのアイコンをダブルクリックして接続ボタンを押す。ピー、ギョロヒョロ…と十数秒間の異音を上げてインターネット接続が確立した。
メールソフトを立ち上げるとなんだかいつもと様子がおかしい。メールの受信に異様な時間がかかっていたのだった。不思議に思って、件名と差出人の欄を確認すると、数通のメールに紛れて1通のメールが目に止まった。お母さんからのメールであった。
「離婚のこと」
件名にはそう書かれていた。悠作は浩紀のことを考えると胸が締め付けられる気持ちがした。メールの本文自体は数行程度の短いものだったけど、何かの画像ファイルが添付されており、これが受信に時間がかかっている原因だった。サイズが1MB以上はある、巨大なファイルだ。14インチのデスクトップ画面一杯に、ジッジッ…とゆっくり画像が表示されていく。
10分以上待ってようやく表示された画像は、あの日お母さんと笑いながら撮った、テーブルの上のみかんの写真であった…。
あれから長い年月が経った今も、あのみかんの写真の意味は不明なままだ。お母さんがただ間違えて添付してしまっただけなのだろうか。いや悠作には何か深いメッセージが隠されていたと思えてならないのだ。
いまだにテーブルの上のみかんを見るたびに、あのお風呂上がりの残り香のような、不思議な淡い感覚を覚える。あれは恋だったのだろうか。決して消し去ることのできない、昔の思い出である。
(了)

 北野とほ (Kitano Toho)
北野とほ (Kitano Toho)
自作小説&エッセイを勝手に不定期連載してます。
雪国在住です。野山を歩くのが好きです。





Copyright(c) 2023 アンダンテ All right reserved.