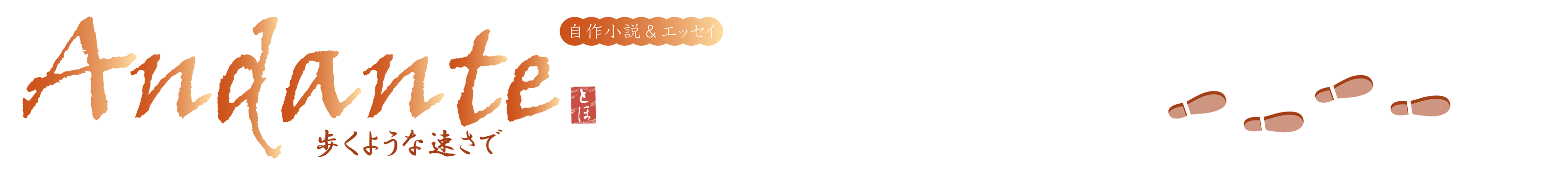第10回 流星群
もし肉体が滅んでも魂は永遠なのだとしたら、そこに刻まれた想いは残り続ける。たとえそれが、宇宙という時間の中でほんの一瞬に過ぎない人生の、たった一年間に起きた人と人との出会いだったとしても。
2013年8月上旬、僕は仙台に向かっていた。表向きの理由は仕事での出張だったが、まだ震災の爪痕が残る東北の地を二十年ぶりに訪れるのにはもう一つ別の理由があった。
仙台は予備校時代に一年過ごしたが、その後は北海道の大学に進学し、札幌で就職してからも仕事が忙しくて訪れる機会がなかった。この日、僕は自宅のある札幌から快速エアポートで新千歳空港に向かい、そこから飛行機で仙台空港に降り立った。仙台空港からJRに乗り換え、もうすぐ仙台駅に到着する頃だ。
「あの震災から二年、街の様子も僕が住んでいた頃とは大きく変わっただろうな」
そう思っていた時、車窓からは見覚えのある広瀬川の流れが見えた。杜の都・仙台の根っこにある本質は、あの有名な歌手が歌っていた頃とさほど変わっていないのかもしれない。
二十年前の1993年の春、僕は実家の函館からこの仙台にやってきた。大学受験に失敗して仙台の予備校に通うため、寮に入ることになったのだ。当時、函館の浪人生は札幌に出ることがほとんどだった。それなのになぜ僕が仙台にきたのかというと、兄が東北大学に通っていたこともあり、両親が心配がって仙台に住むことをすすめてくれたからだ。今から思えば、バブル崩壊直後の時代背景の中、決して裕福ではなかった、いやむしろ貧乏だった両親がよく予備校と寮生活の費用を出してくれたものだと思う。
予備校の寮は男子寮と女子寮があわせて五、六棟あって市内各地に散らばっていたが、向山寮だけは男女共同の寮であった。向山寮でももちろん男女の行き来は禁止されてはいただろうけど、密かに交流は行われていたというのは僕の勝手な憶測である。一方、僕の住んでいた川内寮は男ばかりでむさ苦しくはあったが、広瀬川のほとりにある静かな場所で環境的には恵まれていた。毎朝予備校に向かう途中、広瀬川に架かる仲の瀬橋の広い歩道を自転車で走るのが心地よかった。初夏の午後には緑が濃くなってきた川沿いの木々がキラキラと川面に反射して涼しげな景色を見せてくれた。夜になって勉強に疲れた時は、こっそり寮を抜け出して川のほとりの草っぱらで、買ったばかりのブルースハープを吹いて一人で黄昏れたりしていたのだけど、そんな時に限って実家の母から寮に電話がかかってきて、門限を過ぎても部屋にいないことがバレてしまい、寮長に叱られるということもしばしばであった。
「たまには家に電話しなさいよ。寮にも公衆電話あるんでしょ。お兄ちゃんも留守電にメッセージいれても全然返事よこさないし」
電話越しの母からの小言だ。確かに寮の玄関ホールの横には公衆電話が一台設置してあり、いつでも使えるようになっていた。兄は大学生活を謳歌しているようだったけど、卒業を控え、バイトなどもあってなかなか忙しいのかもしれない。母親としては息子二人が仙台にいるもんだから気が気でないのだろう。
「ごめん、電話しようと思った時にいつも誰かが使っててさ、やっと終わった頃には消灯時間すぎてるんだわ」
僕の言い分はあながち嘘ではない。寮生は百人以上いたし、夕食後には必ず誰かが公衆電話を使っていた。それは理由の一つだったけど、本当は高い市外通話料金が一番のネックだった。仙台から函館の市外通話は夜でも一分間で六十円だったはずだから十分間も通話すれば六百円以上はかかってしまう。
「どうせ、通話料金を気にしてんでしょ。いいから気にせず電話しなさい」
やっぱり母にはかなわない。でも今はその時の母の気持ちがよくわかる。
「今、お父さんにかわるからね」
「うん」
父はいつも多くを語らないけど、僕の事を一番心配してくれていたのだと思う。
「体調、ちゃんと管理してるか」
「うん」
「お前だったら大丈夫、お父さん、いつもお前のがんばり見てたから何も心配してないぞ」
「うん」
「なんか困ったことあったら言えよ、いつでも電話してこいよ」
「うん」
わざと明るい口調で励ましてくれる父の気持ちが痛いほどよく伝わった。本当は言いたいことはたくさんあった。でも言えなかった。父親に対する照れ臭さだったのか、それともお金がかかる予備校生であることへの申し訳なさだったのか。
それから約一週間後、実家から小包が届いた。肌着のほか、函館のイカ煎餅など日持ちのするお菓子が詰まった段ボールの底に封筒があり、テレホンカードが何枚も入っていた。
川内寮は五階建ての建物だった。入り口の玄関ホールをあがってすぐ右横にエレベーターが一基あって、一階から五階までつながっていた。エレベーターを降りたすぐ左には各階に共同の洗面所とトイレがあった。三階の洗面所の奥が寮全体の洗濯スペースとなっており、洗濯機はおそらく十台くらいはあったが、休日の洗濯機はまさに争奪戦だった。僕の部屋はその洗濯場を出て、二十メートルほどの狭い廊下を進んだ東側の奥の三五二号室であった。トイレまで遠いのはやや不便だったけど、その代わり小さな洗面所が僕の部屋のすぐそばにあって寝る前の歯磨きなどはそこですませることができた。
部屋は四畳半くらいの間取りで机とベッドしかなく、もちろんテレビなんてあるはずもない。でも、寮生のうち何人か、小さいテレビを部屋に持ち込んでいる輩がいた。テレビ用のアンテナや端子など部屋にはなかったはずなのに、どうやって見ていたのか今でも不思議でならない。僕にとっての唯一の娯楽は、ラジカセで聴く音楽やラジオ番組であった。
このラジカセも僕が浪人する時に、父が買ってくれたものだった。本体の上にスピーカーが左右に二つついていて、音楽の種類に応じてサラウンドだったり、重低音だったり細かく音質を設定して角度を調整できるようになっていた。本当はこんなに高価なもの要らなかったのに、父は受験勉強は気晴らしが大事だからと、このラジカセを選んでくれたのだ。高校二年の時に兄からもらった槇原敬之の「どんなときも。」のCDシングルや、FMで流れてくるヒット曲をカセットテープに録音して繰り返し聴いたものだった。
僕は浪人することになった時から、これからの一年間、友達は作らないと決めていた。なりふり構わず勉強に集中して、なんとしても来年こそ志望大学に合格するのだと。
考えてみれば浪人生ほど空しいものはない。もう高校生でもなく、だからといって学生とも言えない、何とも宙ぶらりんな身分だ。しかも浪人したら必ず大学に入れるかというとそんな保証はどこにもない。常に不安との背中合わせなのだ。
僕たちの世代はちょうど第二次ベビーブーム、いわゆる団塊ジュニアの世代だったから浪人人口もかなり多かったと聞いている。たぶん当時、全国で二十万人弱が僕と同じ年に浪人していたはずだ。逆に言うとそれだけ受験戦争が熾烈だったのだ。二浪、三浪の人もたくさんいた。予備校内で「さん」付けで呼ばれている人は間違いなく二浪以上の先輩だった。そういう人たちは予備校の事を知り尽くしているだけでなく面倒見のいい人が多かったから、一浪生からは尊敬の眼差しで見られていた。二浪や三浪の人に尊敬の念を抱くというのは常識的に考えると何とも不思議な感覚だと思える。それはあたかも、刑務所で服役している囚人たちの中では、より重い罪を犯して刑期の長い者の方が一目置かれるという心情に似ているのかもしれない。
予備校の校舎はいつ出来たのかわからない古い建物で、通路も狭かったから授業の合間には教室を移動する予備校生たちでごった返し、歩くのもままならない状況が常だった。エレベーターに乗ろうものなら、1.5メートル四方くらいの狭い空間にぎゅうぎゅう詰めになってしまう。そんな狭いエレベーターに乗っている時、なんとなく上部にある現在位置を示す階表示ランプを見てしまうのだけれど、そこには誰の仕業か、「こっち見んな」とマジックで書かれていたから、結局、下を向くしかなかった。
予備校生活にも少し慣れてきたある日の夕方、寮で勉強をしていると部屋のインターホンが鳴った。
「玄関にお兄さん来てるよ」
寮長からの伝言だ。
僕は急いでシャツをはおると階段をかけ降りた。寮の広めの玄関ホールに久しぶりに会う兄の姿があった。見た目はあまり変わってない。いや少し太ったか。
兄は僕を寮の外に連れ出すと、
「今から俺んち来い!」
と語気も強めに叫んだ。兄が一人暮らしをしているのは、太白区の青山という場所だったはずだ。
「いや、これから晩飯だし、門限もあるし。大体、もう交通機関ねぇべや」
そんな僕の戸惑いをかき消すように兄はバイクのヘルメットを僕に投げてよこした。
「これで行けば大丈夫!」
自信満々に答えた兄であったが、バイクといっても彼が乗っているのは、50ccの原付である。原付の二人乗りは道交法違反というのは僕でも知ってる。
「大丈夫だって」
勢いに押されるがまま、原付の後ろにまたがった。交通量の少ない道を選んで迂回しては行ったものの、途中の急な坂道でパワーが足りず、結局歩いて登ることになった。
「友達できたか?」
帰り道、ヘルメット越しに兄が言った。
「予備校で友達作ってもしゃーねーべや」
「そんなことねって。勉強ばっかりしてたら却ってストレスたまるぞ」
別れ際に兄は言った。まだ肌寒い四月の風が僕の心に沁みた。
あっという間に一カ月が過ぎた。ある日の深夜、僕が洗面所で歯を磨いていると、一人の寮生が突然話しかけてきたのだった。
「どっがらきたの?」
馴れ馴れしく話しかけて来た彼に対して、
「いや…函館だけど」
と答えてはみたが、その時、僕はさっさと歯磨きを終えて彼から逃げようと思っていた。予備校の寮で誰かと話すなんて時間の無駄だ。さっさと寝て明日に備えた方がいい。
「へぇ、函館からなんて珍しいな」
「別に珍しくなんかねぇべや、じゃおめーはどこよ?」
無視するつもりだったのに、反射的に僕は聞き返してしまった。
「からぐわ。たがだの近くだ」
ハハハと白い歯を見せて彼は笑った。
何を言ってるんだと僕は思った。からぐわ?たがだ?そんな場所は聞いたこともない。
「函館っていったら観光名所たくさんあっていいなぁ」
彼は続けた。
「じゃ、からぐわって所には何あんの?」
矢継ぎ早に僕が問い返すと
「津波体験館。それしかねぇ」
名前を小杉と名乗った彼は、再び白い歯を見せて笑った。
怪訝そうな顔をしていたであろう僕の顔に、思わず笑みがこぼれるのがわかった。それからというもの、僕たちは、機会があるたびに話をするようになっていった。
夏も近づいたころ、僕は化学の講義に出席していた。どの講義も座席は自由なのだけど、この時期になってくると誰が決めたわけでもないのに、知らぬ間に座る席が決まってくる。僕がよく座る席の右前方には、いつも一人で座っている女の子がいた。見た目は地味な感じなのだけど、色白で切れ長の目が知性を感じさせ、まっすぐ伸びた黒い髪が美しく、しゃんと伸びた背筋が印象的だった。
「どこから来た人なんだろう」
いつしか僕はこの化学の講義が楽しみになっていた。
土曜日の晴れた午後、寮の屋上に洗濯物を干して部屋に戻った僕はいつものように机に向かって勉強をしていた。その時だった。
コンッ、コンッ
窓に何かがぶつかる音がする。
東側にある僕の部屋の窓はちょうど中庭を隔てて対面にある、西側の洗濯場と向かい合わせになっていた。なんだろう、と窓を開けて目を凝らしてみると、小杉が洗濯場の窓からこちらに向かってエアーガンを構えている姿が見えた。さっきから窓にコツコツ言っていたのは、彼が放ったBB弾であった。
「今日の晩飯のあと、キソカイ教えてくれん?」
キソカイというのは数学の科目の一つである基礎解析のことだ。僕は理系だったけど文系の小杉は三角関数が苦手だったらしい。せっかく頼んでくれたのだからと、言われるままに夕食後、彼の部屋を訪れることにした。考えてみれば彼の部屋に行くのは初めてだ。部屋は三〇三号室で同じ三階だったが、西側の洗濯場の奥にあり僕の部屋とはちょうど建物の対角線の位置にあった。
「おい小杉、入るぞー」
ノックをしてドアをあけ彼の部屋に一歩踏み入れたとき、僕は唖然として言葉を失った。部屋の床一面に、あたかも絨毯のように、エロ本が所せましと敷き詰められていたのだった。
戸惑う僕の姿を見て小杉はゲラゲラと笑った。一冊貸してやろうか?という彼の申し出を僕はかろうじて丁重に断った。しかし心の底から湧き出てくる愉快さを抑えることはできず、二人で大声で笑った。彼は三角関数は苦手だったけれど、少なくとも、女体の神秘については、僕の百倍以上はよく理解していたに違いない。
次の週、化学の講義に出席すると、いつもの右前方の女の子の横に知らない男が座っていた。しかも馴れ馴れしく彼女に話しかけているように見える。
「なんだ、あいつ」
痩せ型で黒縁メガネのいかにもオタクっぽい男をみた瞬間、僕は思わず心の中で舌打ちしたが、見て見ぬふりをするしかなかった。有機化学の計算問題がぜんぜん頭に入らなかった。
「好きなんだべ?」
耳元で囁く声が聞こえた。びっくりして振り返るとそこにはニヤニヤ笑う小杉の姿があった。
「おめぇ!文系なのになんでここにいんのよ!」
図星をつかれた僕が思わず声をあげると周囲の視線が一斉にこっちを向いた。僕たちは肩をすくめて、すみませんと教室のみんなに頭を下げた。右前方の彼女もこちらを向いて、その細い両目で微笑んでくれた。
その日からの小杉の行動は早かった。彼の調査によると、彼女の名前は白井真奈というらしい。一浪生で福島の女子高出身だとわかった。一方、隣に座っていたのは田村という男で、秋田の高校を卒業し医学部を目指しているそうだが去年は別の予備校で浪人したものの、失敗して現在は二浪目なのだという。あんな女たらしオタクが医者になったら世も末だ。さらに小杉によると二人は向山寮から通っているとのことだった。やっぱり向山だった。男女共同の寮は思った通りろくなことがない。
それからも小杉は事あるごとに僕に対し、白井真奈に想いを伝えろと冷やかしてきた。その度に僕は軽くあしらった。時はもう七月、予備校の前期の授業も終了し、そろそろ夏期講習が始まろうとする時期だった。
夏休みが始まってすぐ、寮でちょっとした騒動が起きた。廊下がやけに騒がしいと思っていたとき、僕の部屋をドンドンと叩く音が聞こえ、あわててドアを開けてみると小杉が肩で息をしながらそこに立っていた。
「寮にゴキブリいるぞ!」
北海道にゴキブリはいないから函館出身の僕はゴキブリを見たことがなかった。驚いた僕は好奇心もあって小杉と一緒に廊下に飛び出した。すでにたくさんの寮生がその小さな黒い敵を追いかけていたが、小杉はこちらに近づいてきたゴキブリを見つけるや否や、
「田村、しね!」
と、履いていたスリッパでゴキブリを叩きつけた。しかしゴキブリは怯む様子もなくすごい勢いで廊下を駆け回った。
「何やってんね、おめえもやれや!」
小杉の勢いに押されて、僕も思わず、
「田村ぁ、しねぇ!」
と、笑いながら叫んだ。結局ゴキブリは退治することができなかったが、弱った隙にエレベーターのドアを開けて中に押し込み、五階のボタンを押して上の階に転送することに成功した。
それからしばらくして夏期講習が始まった。夏期講習は市内の現役高校生も授業に参加するので、ただでさえ狭い予備校の校舎がさらに窮屈になる。自習室も満席に近くなり、エアコンも効いていないので、もっぱら自習は図書館ですることが多くなった。
そして図書館の隅で参考書を開く僕の隣には、一緒に勉強をする真奈がいた。
二週間前の夜、部屋のインターホンに小杉から連絡があり、一階の玄関ホールに降りて来いと呼び出された。
「いいか、今から向山寮に電話するぞ」
狐につままれたような顔をしている僕を鼻であしらうかのように、小杉は手元のメモを取り出して公衆電話にテレホンカードを入れ、向山寮の番号を押した。そして僕の名前を騙って白井真奈を電話口に呼び出したのだった。
「白井です。あのぅ、どちらさまでしょうか」
突然受話器を渡された僕は何を話していいのかわからず頭の中が真っ白になった。しかし電話越しとはいえ初めて聞いたその柔らかな声に、僕は勇気を振り絞ってこれまでの経緯と想いを伝え、直接会う約束をすることができたのだった。そんな僕の横で小杉は、いつもの通り、白い歯を見せながらニコニコとわらっていた。
それから僕と真奈は週に二、三回は待ち合わせをして会うようになった。図書館などでの勉強がほとんどだったけど、たまにデパートに買い物に行ったり、喫茶店に入ってコーヒーを飲んだりした。心配の種だった例の田村という男は、一方的に近づいて来ていただけだったらしい。
真奈は故郷の福島の事をいつも楽しそうに話した。自宅の窓から季節ごとに姿を変えてみえる磐梯山や、南相馬という町に住んでいる祖母との思い出を語るとき、彼女の整った顔立ちがいつも優しくほころんだ。
折しも仙台は七夕祭りの季節だった。仙台の七夕祭りは毎年八月六日から八日に開催され、街中が色とりどりの鮮やかな七夕飾りで彩られる。
「七夕祭りのイベント、一緒に行かない?」
少しためらいがちに僕は真奈を誘った。受験生が仙台の七夕祭りに行くと、失敗するというジンクスがあるのは聞いていた。でもそんなジンクスよりも僕は彼女のそばにいたかった。一緒に過ごす時間を作りたかった。
「私も行きたい」
真奈は僕の目を見ながら照れくさそうに微笑んだ。
その夜、僕たちは一緒に広瀬川のほとりを歩いた。辺りはもう暗くなっていて寮の門限が迫ってきていた。空には満天の星ぼしが煌めき、夏の大三角が天頂に光っている。こと座のベガは織姫、わし座のアルタイルは彦星。七夕の夜、年に一度しか会えなくても、無限に続く時間の中では、一年も一瞬に過ぎないのだ。
宇宙の片隅で、僕は真奈の小さな身体を強く抱きしめた。温かい肌のぬくもりが僕の腕に伝わってきた。
その時だ。僕たちは北東の空から無数の星ぼしが次々と流れ落ちてくるのを見た。
「ペルセウス座流星群だ!」
僕は星明かりに照らされた真奈の瞳を見つめた。これから先、もしも二人を分かつものが現れたとしても、今この時の気持ちはまぎれもない真実だ。どれだけの時が流れても、魂の中に存在し続けるのだ。
それから数日後、予備校から寮に戻った僕は部屋のドアに貼られた付箋を見つけた。メモには何も書いていなかったけれど、差出人はあいつに違いなかった。
「おい小杉、入っていいか?」
僕は三〇三号室のドアをノックしたが返事がなかった。おかしい、まだ風呂にでも入っているのかな、それとも談話室か。不思議に思いながらドアノブを回してみると部屋の鍵はあいたままであった。
「なんだ、いたのか」
部屋のドアを開けたとき、僕は異様な雰囲気を感じとった。いつも床に敷き詰められていたエロ本がすべて綺麗さっぱり片付けられていたのだった。いや、そんな事はどうでもいい。小杉が顔を隠すように机に覆いかぶさってうずくまっていたのだった。
初めてみる姿だった。
「どうした!」
驚いて僕は駆け寄り小杉の背中を揺すった。小杉は震えながら泣いていた。今まで僕に笑顔しか見せたことのないあの小杉が、泣いていた。
「俺、予備校やめるわ…」
声を震わせながら小杉は言った。父親の体調が悪化して経済的にも大学進学が難しくなってしまったのが理由だった。実家に戻って漁業の手伝いをすることに決まったのだそうだ。大学進学をあきらめてどうするんだ、一生懸命勉強して公認会計士になるのがお前の夢だったろう。声に出せない想いをこらえながら、僕は小杉の肩を抱きかかえることしかできなかった。
それからすぐに小杉は予備校をやめ、寮を去っていった。
二年前の2011年3月、東日本大震災が起きた。陸前高田を襲った津波で、小杉が亡くなったと人づてに聞いた。
改札を抜け、仙台駅の外に出た僕はゆっくりと空を見上げた。雲一つない空は青く澄みわたり、真夏の風が優しく僕の頬をなでた。遠くから七夕祭りの喧騒が聞こえる。二十年前この街で過ごした、たった一年間の思い出の一つ一つが輝く光となって僕の脳裏によみがえった。そう、まるであの夜の流星群のように。
仙台での仕事が終わったら、唐桑の町を訪れてみよう。大分遅くなってしまったけれど。その時、白昼の空に一つの星が、あの日の彼の笑顔のように、まぶしく煌めいた気がした。
(了)

 北野とほ (Kitano Toho)
北野とほ (Kitano Toho)
自作小説&エッセイを勝手に不定期連載してます。
雪国在住です。野山を歩くのが好きです。





Copyright(c) 2023 アンダンテ All right reserved.